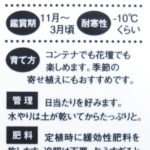植物は水と光と空気、そして適温であればそれなりに育ってくれますが、元気に育てるためにはバランスの良い肥料を与えなくてはいけません。
ひと口に肥料といっても固形のものや液体のもの、即効性のものや緩効性のものなどたくさんの種類があります。今回はそれぞれの肥料の特徴などを書いてみます。
肥料について
自然界の肥料と自分で育てる植物の肥料
自分で育てている植物には定期的に肥料を与えますが、誰も管理していないような野原で育っている植物に誰かが肥料を与えているなんていう話は聞きません。肥料を与えていないのに増えていきますし花も咲かせます。
また野生植物が必要とする栄養分より、園芸品種の場合は大きな花を咲かせたり実を付けたりするため多くの栄養分を必要としますので人工的に与えてあげなくてはいけません。
植物にとって必要な栄養素
植物は17種類の栄養素から構成されています。
これらの17種類のうち炭素、酸素、水素については水や空気中から吸収されますので、なにもしなくても問題ありません。しかし残りの14種類に関してはなんらかの形で補わなくてはいけません。
特に窒素、リン酸、カリウムは【肥料の三要素】といわれ大量に必要とします。
窒素(Nitrogen)リン酸(Phosphoric acid)カリウム(Kalium)
頭文字をとってNPKと略します。
カルシウム、マグネシウム、硫黄は中量要素といわれており、大量要素の次に必要な栄養素です。また鉄、マンガン、ホウ素、亜鉛、モリブデン、銅、塩素、ニッケルは微量要素といわれ、大量にはいりませんが微量程度必要です。
植物はこれらの栄養素をバランスよく与えることが健全に育つことに繋がります。特に大量に必要な栄養素は肥料として定期的に与えなくてはいけません。
肥料の種類を大きく分けると2種類
肥料は化成肥料と有機肥料に分けられ、それぞれの特徴は次のようになります。
化成肥料
鉱物などの無機物を原料としたものを無機質肥料といいます。
化成肥料はすぐに根に吸収される速効性のものが多く、誰にでも扱いやすいのが特徴で、成分比や形はさまざまです。

固形肥料
速効性のある化成肥料ですが、加工することで緩効性肥料にもなります。固形肥料は土に置いたり土に混ぜたり、ばらまいて使う肥料です。
速効性化成肥料の場合、すぐに溶けてしまうため肥料障害を起こすこともありますので、使用回数や使用量には注意が必要です。しかし緩効性化成肥料は、肥料の表面をコーティングしたり、溶け出す量をコントロールしたりしてゆっくり溶けていくように加工してあります。効果は数カ月から数年続くものがありますので、育てている植物によって使い分けるようにしましょう。
液体肥料
液体肥料には原液をそのまま使うものと、水で薄めて使うものがあります。
薄めずに使う肥料
薄めず原液のまま使う肥料は最初から植物に適した状態の液体が入っています。とても手軽で便利なのですが、たくさんの植物に与えようとしたら割高になります。
薄めて使う肥料
水で薄めるタイプの肥料は高濃度の成分になっていますので、育てている植物に合うように濃度の調整を行ってから与えます。ほとんどの場合500倍とか1000倍に薄めて使用するため、1つあればけっこう長持ちします。
スプレータイプの肥料
養分を葉から吸収させる葉面散布用の肥料です。根が弱って肥料を吸収できない時や、葉色が悪い時などに使うと効果的です。吸収を良くするために先に葉を洗うか拭くかをしたあと、葉が乾いてからスプレーしてください。

あくまでも肥料です。葉水の代わりに与えないようにしましょう。
スティックタイプの肥料
プランターや鉢に差し込むだけの肥料です。
土に差しておくと徐々に成分が溶けていき、効果が一定期間続きます。ハンギングバスケットや寄せ植えなどに数か所差し込んでおくとバランスよく生育してくれます。また庭木用のものは追肥のための穴を掘らなくていいので便利です。水生植物用のスティック肥料もあります。
有機肥料
植物や動物など、天然のものを原料にした肥料で微生物の力を利用して分解発酵させ根から吸収させます。

油かす
油かすは植物の種から油を取った後に残る搾りかすのことで、いろいろな種類のものがありますが、大豆や菜種が一般的です。肥料の三要素である窒素、リン酸、カリウムのうち窒素分が多いのが特徴で、ほかの肥料と合わせて使うことが多いようです。
発酵前の段階では臭いがします。土に入れる時は深めに穴を掘って上から土を被せましょう。マルチングをすることも臭い対策に効果があります。
骨粉
骨粉は豚や鶏などの動物の骨を乾燥させてから粉砕したものです。少しの窒素とたくさんのリン酸を含んでおり、油かすや草木灰などと一緒に混ぜて使われます。カリウムはほどんどありません。
ゆっくりと時間をかけて効いていく肥料なので、追肥としてではなく元肥として使います。
鶏糞
ニワトリの糞を加熱、乾燥、発酵させたもので、三要素である窒素、リン酸、カリウムが比較的バランスよく含まれた肥料です。
ただ発酵が不十分なものだと独特な臭気を出し、ガスで根を傷めることになりますので、根に直接触れないように施してください。臭いが気になる場合はペレット状に加工されたものを選ぶと良いでしょう。
魚粉
魚粉は魚を乾燥させて粉砕したものです。窒素とリン酸を多く含んでいますが、カリウムは含まれていないため草木灰などと一緒に使うようにしてください。
魚粉もなかなかの臭気がありますが、臭いを抑えた商品もあるようです。
草木灰
落ち葉や枯草などの草木を燃やしてできた灰のことでカリウムを多く含んでいます。同じ葉を使った腐葉土と違って有機物が燃えてなくなったもののため、残ったカリウムが多くなっています。
アルカリ性なので、酸性になった土壌を中和させるためにも使われます。
米ぬか
玄米を精製する時に取り除く外皮のことを米ぬかといいます。
米ぬかには三要素である窒素、リン酸、カリウムのほか、ビタミンやミネラルも豊富に含んでおり、肥料としてバランスがよく、微生物の活性化も促してくれます。しかしタンパク質も多く含んでいるため虫を寄せ付けやすく、カビも発生することもありますので使う際には注意してください。

米ぬかは昔から美肌に良いといわれていて、石鹸の代わりにぬか袋というものを使って体を洗ったりしてきました。美肌以外では肥料にも使われます。
肥料を施す時の注意点
肥料を頻繁にたくさん与えるといっぱい花が咲くとか、大きく成長するということはありません。適切な量の肥料を適切な時に与えるとたくさん花が咲き、大きく成長してくれます。
よく何日に一度肥料をやればいいですか?ということを聞かれますが、その植物によっても季節によっても状態によっても異なるため、何日に一度ということは分からないのです。
液体肥料はつい適当な割合で薄めがちですが、ある程度はきちんと量って作るようにしてください。3Lのジョウロで量った場合、1000倍ならば3ccの原液を、500倍なら6ccの原液を溶かします。ジョウロのほか、バケツやペットボトルなど水量がわかるものを使って希釈液を作ると良いと思います。

水で薄めた状態での作り置きは成分が変質することがありますので、作った液肥はその日のうちに使い切ってください。
また有機肥料の場合、臭いの強いものも多くあります。
これは私の子供の頃のお話ですが、私の実家は大阪市内にあり、いわゆる住宅密集地です。近所にベランダで花か野菜かを育てていらっしゃるお家があって、そのお家は有機肥料に拘っていらっしゃるらしく、常に肥料の臭いが近所中に漂っており、窓を開ける季節は家の中まで臭いが入ってきて大変でした。
ご近所ということもあって、どのお家も文句を言いに行くことはなかったようですが、できれば住宅地でお使いになる肥料は臭いの強いものは避け、ペレット状に加工されていて臭いがないか、あっても少ない肥料をお使いになられたほうが揉め事に発展しないのではないかと思います。
化成肥料と有機肥料の使い分け
化成肥料と有機肥料を比べると有機肥料が自然栽培らしくていいように思われがちですが、必ずしもそうではありません。
上手に肥料を使い分けて植物を育ててくださいね。