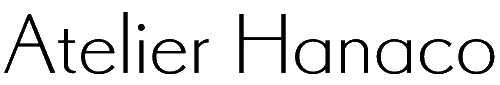アスパラガスは野菜として販売しているのはよくご存じだと思います。しかし花屋や園芸店でも観葉植物としてアスパラガスを販売しています。
観葉植物のアスパラガスを育てていたら、いつかは食べることができるアスパラガスに成長するのでしょうか。
アスパラガスについて
キジカクシは漢字では雉隠と書きます。名前の由来ですが、茎の上部の葉がたくさん茂って雉を隠す程であるということによります。クサスギカズラは臭すぎる蔓(笑)ではなく草杉蔓と書きます。
アスパラガスには食用と観賞用があります。
鑑賞用のアスパラガス

よく見かける観賞用のアスパラガス
上の写真はアスパラガス・スマイラックスですが、ほかにも次のような品種があります。
- アスパラガス・ナナス
和名でシノブボウキ(忍箒)といい、代表的な観葉植物のアスパラガスです。つる性で棘があり姿がとても涼しそうです。 - アスパラガス・マコワニー(ミリオクラダス)
細長い葉が集まってまとまり、丸く見えることから別名ポン・ポン アスパラガスと呼ばれています。和名でタチボウキ(立箒)といいます。 - アスパラガス・スプレンゲリー
杉のような葉をしていることから和名でスギノハカズラ(杉葉蔓)といいます。棘もあります。 - アスパラガス・スマイラックス
茎が蔓状に伸びて2m~3mくらいになります。和名でクサナギカズラ(草薙蔓)といい、葉はほかのアスパラガスより大きいのが特徴です。私はウエディングブーケを作る時に切り花のスマイラックスをよく使いました。棘はありません。

写真は趣味の園芸からお借りしています。写真引用:趣味の園芸
何度か「葉」と書きましたが、実際は葉ではなく枝が葉に見えるように変化したもので「仮葉」や「葉状枝」といいます。

本来の葉は茎の付け根の部分に小さな鱗片や棘のような形になって残っているだけなので、仮葉(葉状枝)で光合成を行います。
鑑賞用のアスパラガスの育て方
水やりは土の表面が乾いたらたっぷりと与えます。肥料は月に1~2度、速効性の液体肥料を与え、春と秋の生育期には緩効性肥料を1度与えます。茎が伸びすぎた時は切り戻しをし、植え替える場合は5~9月頃に行いましょう。
よく育ち、育てやすいので失敗も少ない観葉植物だといえますが、夏の葉焼けだけは気を付けた方がいいですね。
野菜のアスパラガス
食用のアスパラガスの旬は4~6月頃ですが、輸入などもありスーパーなどでは1年中販売しているお馴染みの野菜です。
日本へは江戸時代に渡来し、オランダ船で来たことと日本に自生していたキジカクシに似ていたことから「オランダキジカクシ」と呼ばれました。
野菜のアスパラガスの種類
- グリーンアスパラガス
一番メジャーなアスパラガスです。カロテン、ビタミンC、ビタミンE、ビタミンB群、ルチン、アミノ酸の一種のアスパラギン酸を含む緑黄色野菜です。アスパラギン酸は疲労回復、ルチンは高血圧などの生活習慣病予防に効果があります。 - ホワイトアスパラガス
水煮にして缶詰にするほか、収穫してすぐに茹でて食べます。 - 紫アスパラガス
アントシアニンを含んだアスパラガスです。加熱すると濃緑色になります。 - ミニアスパラガス
グリーンアスパラガスを早どりしたもので、柔らかいので皮むきは不要です。

アスパラガスのどこを食べているか?ですが、食べているのは茎です。ところどころに付いている三角形の部分はハカマといって退化した葉です。
ハカマの部分は少し硬いので、ピーラーで皮むきをすると食べやすいです。
野菜のアスパラガスを植えたままにするとどうなるか
アスパラガスは地下茎で育っていく植物です。収穫する時に全てを収穫せずにある程度残しておくと、夏になると茎が伸びて葉(葉状枝)が出てきます。


葉(葉状枝)は日光を浴びて翌年のために根に栄養を溜めます。
育てている人に聞いてみたところ、苗を植えてもだいたい3年目くらいからしか収穫できないそうです。しかしそのあとは10年間くらい収穫ができるのだそうです。
アスパラガスにはいくつも品種がありますが食用になるのはAsparagus officinalis(アスパラガス オフィキナリス)、和名でオランダキジカクシだけです。
ということなので、観葉植物としてのアスパラガスを成長させても食用のアスパラガスにはなりません。
野菜のアスパラガスは美味しいですが観葉植物のアスパラガスも涼しそうに見えるので夏にお勧めです。