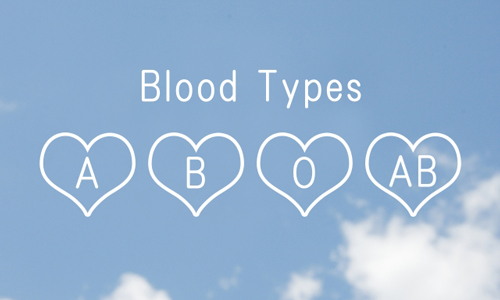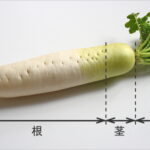皆さんの血液型は何型ですか?
A型は几帳面だとかB型は変わり者だとか、O型は大雑把でAB型は二面性があるんでしたっけ?血液型占いって人間を4パターンに分けただけなので信憑性は全くありませんが、合コンなど初対面の人とでも盛り上がりやすい話題のひとつなのかもしれませんね。
今日のお話は植物と血液型についてです。
植物にも血液型がある?
そもそも植物には血液がありません。それなのに血液型があるなんて嘘みたいな話ですがちゃんとあるんです。それも人間と同じようにA型、B型、O型、AB型の4つに分かれています。
血液がないのにどうやって調べるのか不思議ですよね。
しかし全ての植物の血液型を測定できるというわけではなく、全植物の約10%程度しか判明していないそうです。では判明している植物で代表的なものを見てみましょう。
A型の植物
- アオキ:常緑樹で耐寒性があり、冬になると赤く艶のある実をつけ庭を彩ります。
- ヒサカキ:常緑小高木。榊の代用として神事に使うこともあります。
- キブシ:北海道西南部、本州、四国、九州及び小笠原諸島や沖縄に分布する落葉樹です。
B型の植物
- イヌツゲ:日本全土の山野に見られるモチノキ科の常緑低木です。
- ツルマサキ:沖縄を除く日本全国と朝鮮半島及び中国の山地に分布する常緑のツル性植物です。
- アセビ:ツツジ科の常緑低木で、日本に自生し観賞用に植栽もされています。
- セロリ:野菜のセロリです。セリ科の一年草または二年草です。
O型の植物
ツバキとサザンカは同じツバキ科の植物ということもあってよく似ています。血液型とは関係ないですが見分け方を少し…。
- ツバキ:江戸時代から庶民に親しまれている冬の花です。開花は12月から4月で散る時は花首から落ち、鋸葉が浅いです。
- サザンカ:初冬から冬にかけて花を咲かせます。開花は10月から12月で散る時は花弁が散り、鋸葉が深いです。
ダイコン、ゴボウ、キャベツ、イチゴ、ブドウ、ナシはよく知っていて口にしている野菜や果物です。
AB型の植物
- バラ:バラは花の女王とも呼ばれプレゼントによく使われます。
- スモモ:バラ科の中高木で、実は桃より酸味があることからスモモという名前になりました。
- ソバ:タデ科ソバ属の一年草です。
血液型で色が変わるモミジ
秋になると紅葉してくる植物といえばモミジです。
しかしモミジはカエデとよく似ていますし区別が付きにくいですが、植物学的にはモミジはカエデ属に入っており、その中にイタヤカエデやハウチワカエデなどと並んでイロハモミジやオオモミジがあります。
紅葉の季節のモミジは赤い葉や黄色い葉があります。この色の違いは血液型が関係しています。


紅葉するまでのカエデはクロロフィルという物質で緑の葉に見えています。それが秋になるとクロロフィルが分解され葉の色が無くなっていきます。そうするとアントシアニンやカロテノイドの働きが強まり、葉の色を赤色や黄色に変えていきます。
秋になり紅葉を目にしたとき、色の違いは血液型の違いなんだと思って見てみると面白いかもしれませんね。
日本人の血液型はA型が約40%、O型が約30%、B型が約20%、AB型が約10%といわれています。それに対して植物の血液型はO型がとても多く約80%、次いでAB型だそうでA型とB型は希少なようです。
ちなみに私はO型なのでダイコンやゴボウやキャベツと仲間です。
今回は植物の血液型についてのお話でした。